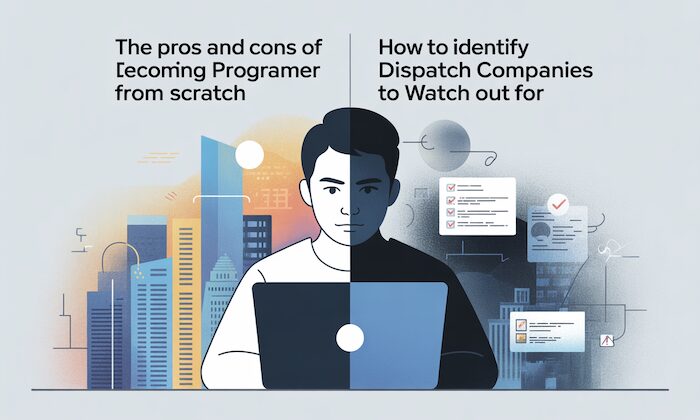
「派遣」という働き方に対して、雇用が不安定・待遇が悪いといったイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、IT業界では派遣という形で多くのエンジニアが現場で活躍しており、キャリアの選択肢の一つとして定着しています。
この記事では、派遣プログラマーの働き方やメリット・デメリットについて整理し、これから目指す方にとって参考になる情報を紹介していきます。
未経験からのキャリア転身
🔴 未経験からのキャリア転身
📌 経験ゼロからエンジニアを目指す人が、現実的な道筋と選択基準を学ぶカテゴリ
└─プログラマーへの歩き方!気になる疑問と勉強方法、求人選びについて
├─【IT業界】そもそも未経験とは?転職にフォーカスすると失敗する理由。
├─未経験から派遣プログラマーになるデメリット・メリット、注意すべき派遣会社とは
├─未経験からITエンジニアになるための6つの面接対策と志望動機!
├─中途採用でITエンジニアになるための4つの秘訣
└─プログラマー未経験者でも研修で育ててくれる会社があるってホント!?
派遣プログラマーとは


派遣の仕組み
派遣とは、雇用契約を結んだ企業(派遣元の企業)から就業先の企業(派遣先の企業)へ文字通り「派遣」され、就業先の企業の仕事に協力することで、その対価を得る働き方です。
企業間では、派遣社員の時給などを決める契約が結ばれ、その契約に応じたお金が派遣元の企業へ支払われます。
登録型派遣(一般派遣)・常用型派遣(特定派遣)・紹介予定派遣の違い
派遣には、3つの種類があります。
1. 登録型派遣(一般派遣)
登録型派遣は、派遣会社に登録しておき、案件ごとに雇用契約を結ぶ働き方です。
働いている期間のみ給与が支払われ、契約が終了すると次の案件に就くまで収入が途切れる可能性があります。
一方で、自分のライフスタイルや希望に合わせて案件を選びやすいという特徴もあり、IT業界では多くのエンジニアがこの形で働いています。
「派遣は不安定」というイメージを持つ方もいますが、スキルを磨いて案件を継続的に獲得できれば、キャリアの一つの選択肢として十分に成立します。
2. 常用型派遣(特定派遣)
IT業界で多く見られるのが、この常用型派遣です。 労働者は派遣会社(派遣元の企業)の正社員として雇用され、必要とする企業へ派遣されて働きます。
派遣期間が終了しても派遣元の正社員であるため、次の派遣先が決まるまで無収入になることはありません。
また、正社員としての雇用契約になるため、有給休暇や社会保険といった基本的な福利厚生も受けられます。
登録型派遣と比べると、安定性が高い働き方といえますが、その分、派遣元企業の就業規則や人事評価の影響を受ける点も意識しておく必要があります。
3. 紹介予定派遣
紹介予定派遣は、派遣期間を経て正社員や契約社員として採用されることを前提とした制度です。
労働者にとっては「職場の実態を見極めてから入社できる」メリットがあり、企業にとっては「スキルや人柄を確認してから採用できる」メリットがあります。
そのため、本来は双方にとって納得感の高い制度といえます。
一方で、派遣業界特有の課題にも注意が必要です。
- 派遣会社が多重構造になっている場合、中間マージンが重なり、労働者に支払われる給与が減るリスクがあります。
- 「紹介予定」と謳いながら、正社員化を前提とせず、短期間の労働力確保として利用されるケースもあります。
- 派遣期間中の教育やサポートが形骸化しており、期待するほどスキルアップにつながらない場合もあります。
紹介予定派遣は制度としては魅力的ですが、実際に利用する際は「過去の正社員登用実績」や「派遣会社の契約形態」を確認することが欠かせません。
派遣プログラマーの年収
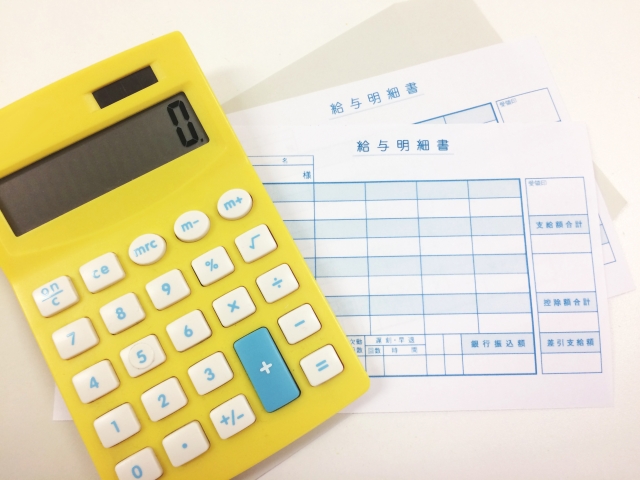
ここでは登録型派遣の年収について紹介します。
プログラマーは専門性が求められるため、派遣社員でも時給相場は比較的高めです。
一般的には 時給2500円~3500円程度 が多く見られます。
仮に「1日8時間 × 月20日」勤務とすると、
月収はおおよそ40万円~56万円、年収換算で480万円~672万円となります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- この試算は1年間途切れなく勤務できた場合を前提としています。契約と契約の間に待機期間が発生すると、その分年収は下がります。
- 福利厚生や賞与は基本的に含まれないため、正社員と比べると手取り感覚は近くなるケースがあります。
- スキルや経験、勤務地域によって時給は変動するため、必ずしも上記の金額に当てはまるわけではありません。
見かけ上は高年収に見えても、トータルで考えると正社員と大きな差がない場合もあるため、条件全体を確認することが大切です。
派遣プログラマーのメリット

派遣プログラマーで働く場合のメリットはどういう点か教えてください。

その他にも、いろいろあるんですよ。
1. 初心者でも採用されやすい

登録型派遣であれば、一定のプログラミング基礎を身につけていれば、初心者でも案件を紹介してもらえる可能性があります。
もちろん、実務経験者と比べると時給など待遇面では劣るケースが多いですが、派遣として働きながら実務経験を積めること自体は大きなメリットです。
現場での経験は履歴書や面接でアピールできる材料となり、将来的に正社員を目指すうえでも有利に働きます。
派遣を「ゴール」と考えるのではなく、実務経験を積みながらキャリアを広げる手段として捉えることが大切です。
2. いろんな会社の開発現場を経験できる
派遣社員が1カ所で3年以上働き続けることは基本的にできないことになっています。
一つの開発プロジェクト限定で派遣され、プロジェクト終了後と同時に派遣期間終了となることもあります。
システム開発の進め方は、企業ごとに違いますし、同じ企業の中でも部署ごとに違う場合もあります。
多くの開発現場を経験できることは、プログラマーにとって大きなプラスになります。
IT企業各社は、どうすれば効率的に品質の良いシステムを開発できるのか、日々試行錯誤しながらシステムを開発しています。
そのノウハウを吸収できることは、エンジニアとして大きな価値があります。
3. 大規模なプロジェクトに関わることができる

大企業のシステム開発の現場でも、多くの派遣プログラマーが活躍しています。
実際に派遣で働いた経験のあるプログラマーに開発実績を聞いたところ、毎日数万人が利用する鉄道の運行を管理するシステムや、社会インフラの制御システムの開発に関わったことがあるということでした。
働いているのは小さな派遣会社だったのですが、大企業が手がけるシステムの開発を経験していることに驚かされました。
開発した本人も、自分が手がけたシステムがテレビで放映されたり、話題になることが非常に誇らしく思えるということでした。
4. 常にプログラマーとして活躍できる
自社で開発をしていれば、いずれマネジメントの仕事をする年齢になり、多くの場合、自然とプログラマーを卒業することになります。
一方、派遣プログラマーの場合、求められるのはマネジメント力ではなく、純粋にプログラミングの技術です。
つまり、プログラミングの技術習得を怠らなければ、生涯プログラマーとして活躍することができます。
5. 大企業や、有名企業で働くことができる

正社員で入るのは難しい大企業や有名企業でも、派遣であれば参画できる可能性があります。
通常では経験できない最前線の技術や、誰もが知るシステムの一部に関われるのは大きな魅力です。
ただし、派遣社員が多く入れ替わるのも大企業の特徴です。大規模な企業ほど「人材の入れ替え」を前提にした仕組みやマニュアルが整備されており、作業が標準化されています。
この仕組みを理解して働くことで、自分が「代替のきく作業者」なのか、それとも「替えがたい立ち位置」にいるのかを把握することができます。
この視点を持っておくと、その後の転職活動やキャリアロードマップを考える上で、自分の立ち位置を明確にできるでしょう。
6. 無理な仕事を断りやすい
派遣社員は雇用契約の相手が派遣元の企業であるため、派遣先からの業務指示が契約内容を超える場合には、派遣元を通じて調整してもらえる仕組みがあります。
そのため、正社員に比べて「契約外の業務を断りやすい」という面があります。
ただし、これは「無理な残業や理不尽な依頼を避けやすい」という意味であり、すべての業務を自由に断れるわけではありません。
過度に強い態度を取ったり、正当な理由のない拒否を繰り返したりすると、契約更新に影響する可能性があります。
大切なのは、派遣元に相談しながら適切に調整してもらうことです。
契約内容を理解したうえで、必要に応じて派遣会社を通じて対応するのが現実的な方法といえます。
7. 人脈が広がる

自社のシステムを開発するプログラマーと比較すると、多くの開発現場に派遣されるプログラマーとでは、人脈の広がりに大きな差がでてきます。
「仕事は会社にくるのではなく、人にくるものだ」と言う話を聞いたことがあります。
実際にプログラマーの派遣の相談をするときは、特定のプログラマーを指定してくることが頻繁にあります。
派遣プログラマーは良い仕事をすれば次々と仕事が舞い込んできます。
また、将来、起業する場合やフリーランスとして活動する場合にも、人脈の広さは大きな武器になります。
8. 時間の融通が利きやすい
これは登録型派遣のプログラマーに言えることですが、自分のライフスタイルに合わせて、就業日数、就業時間を調整ができます。
例えば、子育てをしながら、仕事を両立したい場合、時給の高い登録型派遣のプログラマーは良い選択だと思います。
派遣プログラマーのデメリット



1. ステップアップが難しい
派遣プログラマーとして働く場合、派遣元の企業内での昇進や役職がつくことは基本的に期待できません。
実際の業務時間の大半は派遣先企業で過ごすため、派遣元で管理職としての役割を担うことが難しいからです。
多くの派遣会社では、役職があっても実務権限を伴わない「名ばかり役職」にとどまるケースがほとんどです。
例えば、中小規模の派遣会社では社長と総務担当以外は全員が一般社員という体制も珍しくありません。
この背景には、仕事の指揮権が派遣先企業にあり、派遣元が社内に階層的なマネジメント体制を作る必要がない、という仕組みがあります。
つまり「派遣で働くこと=社内での昇進は難しい」という構造的な制約があるのです。
ただし、これはキャリアが停滞するという意味ではありません。
派遣先で得た経験やスキルをどのように活かすかが重要であり、プロジェクト経験や専門スキルを積み重ねることで、次の転職やキャリアアップにつなげることは十分可能です。
2. 1か所で働ける期間が限られる
2015年の労働者派遣法改正により、同じ組織単位(部署など)で派遣社員として働ける期間は最長3年と定められました。
そのため、どれだけやりがいを感じられる職場であっても、派遣先の直接雇用に切り替わらない限り、同じ職場で長く働き続けることはできません。
ただし、この「3年ルール」は派遣先の企業が労働者を直接雇用する意向を示した場合には転換のチャンスになります。
また、部署を異動すれば再度派遣契約が可能になるなど、実際の運用には例外もあります。
派遣を続けたいのか、正社員を目指すのか、自分のキャリアプランに応じて「3年の節目」をどう活かすかを考えておくことが重要です。
3. 世間の「派遣」へのイメージが良くない
常用型派遣で働くプログラマーは派遣元企業の正社員ですが、一般的に「派遣」の働き方は登録型派遣が知れ渡っているため、常用型派遣が安定した雇用形態であることを説明するのに手間がかかります。
知人は、銀行で住宅ローンを組む際に、仕事に関する質問を受け、四苦八苦したと聞きました。


派遣で働きながら感じた違和感

作業効率の悪い方が高評価?
派遣の場合、不思議なことに、作業効率が悪い人の評価が高くなってしまうことがあります。
例えば、Aさんが1時間で終わらせる作業を、Bさんが2時間もかけて終わらせた場合、派遣先の企業では早く仕事を終わらせたAさんが評価されます。
しかし、派遣元の企業から見ると、Aさんには派遣先の企業から1時間分の対価が支払われ、Bさんには2時間分の対価が支払われます。
つまり、雇用元である派遣元の企業から見ると、会社に利益をもたらしているのは、作業効率の悪いBさんの方になってしまうのです。
極端に言うと、一生懸命働いて定時までに仕事を終わらせた人より、昼間は仕事をしているふりをして深夜まで残業をする人の方が、派遣元の企業での評価は高くなります。
派遣プログラマーは、こういった矛盾を感じながら仕事をしなければならないのです。
ミスを犯しても責めを負うのは自分以外
派遣プログラマーは、派遣先の社員から見れば、”仕事を協力していただいている人”なので、不具合が発生した時に顧客から責めを負うのは派遣先の社員です。
自分が出した不具合で別の人が叱られ、謝罪しているところを見ていると、いたたまれない気持ちになります。
こんな派遣会社には要注意
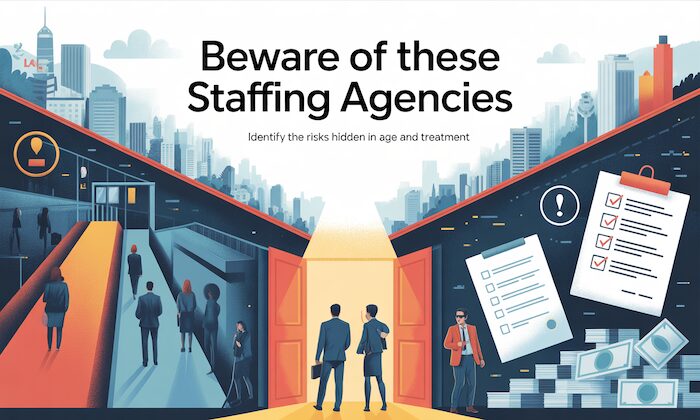


特に次の2点は注意してください。
取引先が1社または2社
派遣会社の中には、取引先の企業が極端に少ない、中には1社だけという企業が実在します。
つまり、社内のエンジニア全員を1つの企業に送り込んでいることになります。
この場合、企業間の力関係が派遣先の企業の方に片寄りすぎてしまい、派遣開始の際に交わす契約内容が、派遣元の企業にとって不利な内容になりやすいです。
派遣先の企業から「あなたたちは、うちから派遣を切られれば立ち行かなくなるでしょう」と言われれば、悪い条件でも飲まざるを得ません。
派遣プログラマーの給料を上げるには、派遣契約で取り決める金額を上げる必要があります。
しかし、企業間の力関係が崩れ、仕事に対して得られる対価が変わらなくなった場合、派遣社員の給与が上がることはありません。
「うちの社員は実績を上げているので、金額を上げてください。そうしないと、別の企業に派遣します」と言えるくらい、派遣元の企業に力がなければ、派遣プログラマーとして長く勤めることは難しいでしょう。
大抵の場合、企業のホームページに取引先企業に関する記載があるため、そちらで確認するようにしましょう。
平均年齢が20代
平均年齢が異様に若い企業にも注意が必要です。
これは、派遣会社だけに限らず、すべての企業に言えることですが、平均年齢が低いということは、その会社で長く働くことはできないと考えてください。
結婚して子どもを育てる年代の社員が少なければ、その企業は何らかの問題で家族を養っていけない、守っていけないと判断され、退職する人が多い企業といえます。
私の知る派遣会社は、新入社員は毎年数名入っているにも関わらず30代目前で退職する人が続出し、平均年齢は28歳前後でした。
退職者に話を聞くと、「基本給が上がらず、将来が不安」「残業代がないと生活できない。この先、体力的に残業ができなくなったら、生活が立ち行かなくなる」といった不安から退職を決意する人が多くいました。
それを事前に見極めるため、社員の平均年齢は必ずチェックするようにしてください。
ただし、新しく立ち上げたばかりの企業は、そもそも年齢を重ねた社員がいない可能性があるため、この限りではありません。
まとめ

派遣プログラマーとはどのような働き方なのか、また、メリットとデメリットについてもご理解いただけたでしょうか。
初心者であれば、実務経験を積むために派遣を利用してプログラミングのスキルを覚えることも、派遣先企業との契約次第で可能です。
また、プログラミング経験者の方でも、多くの企業の開発現場を経験し、自身のスキルアップを図るには、良い選択かと思います。
ご自身のキャリアプランに合わせて、”派遣”という働き方も一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
20代〜30代前半におすすめのITスクール
未経験からプログラマーを目指す方に向けて、特に評判が高いITスクールを3つご紹介します。プログラマカレッジ
10代、20代の方でこれからプログラマーを目指すなら、無料で学ぶことができる「プログラマカレッジ」をおすすめします。受講料が0円で学べる仕組みや、就職支援の内容が充実しているため、最初の一歩として検討する価値があります。テックキャンプ
20代で未経験からエンジニアを目指すなら、短期間で実践スキルを身につけられる「テックキャンプ」も選択肢の一つです。転職成功率97%という実績があり、転職できなければ全額返金保証付き。通学とオンラインどちらにも対応しているので、ライフスタイルに合わせて柔軟に学習可能です。僕のAIアカデミー
「僕のAIアカデミー」は、AIをキャリアや副業に活かす実践型オンラインスクールです。 ただし、流行に任せて安易に選択すると「こんなはずじゃなかった」という後悔につながる危険もあります。その理由を以下で整理します。- トレンドに飛びついただけでは、基礎を飛ばして表面的な操作スキルで終わり、企業で通用しない
- 転職活動では「AIは触れるが設計や基盤はできない」と評価され、キャリアが行き詰まる
- 短期的な期待だけで選ぶと、結局はスキルも収益も身につかず「こんなはずじゃなかった」と後悔する
- 第一階層:ITリテラシー(PC操作・ネットワーク基礎)
- 第二階層:プログラム言語(JavaやPythonなど)
- 第三階層:設計スキル(要件定義・設計書作成・アーキテクチャ理解)
- 第四階層:AP基盤スキル(ミドルウェア・サーバー・クラウド)
- 第五階層:運用スキル(監視・セキュリティ・障害対応)
AIによる副業・起業力を高める実践型スクール【僕のAIアカデミー】








