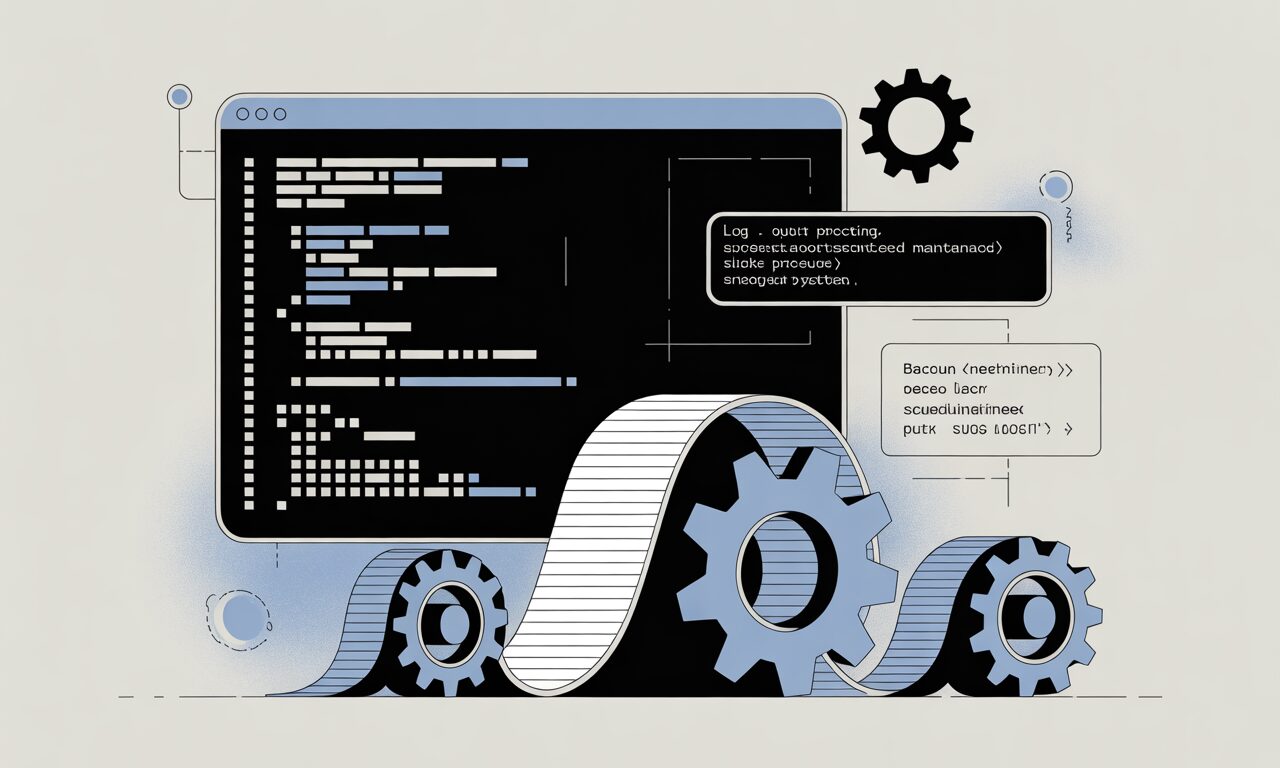Shellの基礎知識(実践編)
基礎で学んだ文法や構文を、実際の業務へと落とし込むステップです。このカテゴリでは、単純なスクリプトの書き方を越えて、「どう設計すれば壊れないか」「どう仕組みとして残せるか」に焦点を当てています。ログ出力、エラー処理、バックアップ、定期実行など、現場で必ず必要になる処理をbashで実装し、運用テンプレートとして再利用できる形に整理しています。
「動かすだけ」から「維持できるスクリプト」へ──ここで学ぶ内容が、日々の運用効率を根本から変えていきます。
Shellの基礎知識
🟡 Shellの基礎知識(実践編)
📌 現場レベルの自動化スクリプトを実装しながら学ぶ実戦形式。
└─【Shellの基礎知識】設計から運用まで自動化の仕組みを解説|RHEL系Linux対応
├─基本共通
| ├─【【Shellの基礎知識】簡単なログ出力ロジックを作ってみました。
| ├─【【Shellの基礎知識】シェルスクリプトの作成を時短!テンプレートで効率化する方法
| └─【【Shellの基礎知識】共通関数定義クラスの完全ガイド!設計から実践まで徹底解説
├─ 開発環境構築
| ├─【RHEL系Linux】開発サーバー初期設定スクリプトの完全自動化
| ├─【RHEL系Linux】Apache+Let's Encrypt 自動構築スクリプト|バーチャルホスト対応
| ├─【RHEL系Linux】Tomcatを自動インストール・設定するスクリプトの作成と活用法
| └─【RHEL系Linux】PostgreSQLを自動インストールするシェルスクリプトの使い方
└─ 運用・保守
├─【RHEL系Linux】任意サービスを簡単制御!汎用サービススクリプトの活用術
├─【RHEL系Linux】ファイルやログを自動圧縮する汎用スクリプトの実装と活用法
├─【RHEL系Linux】リソース(CPU・MEM)監視スクリプトで使用率・異常を検知の仕組み
├─【RHEL系Linux】中間ファイル連携を完全制御するファイル転送スクリプト
├─【RHEL系Linux】信頼性を重視した完了保証型ディレクトリ転送スクリプトの設計と実装
├─【RHEL系Linux】ディスク使用率を自動監視するシェルスクリプトの実装
└─【RHEL系Linux】サーバーの障害検知と自動通知|systemdログ監視の実装例