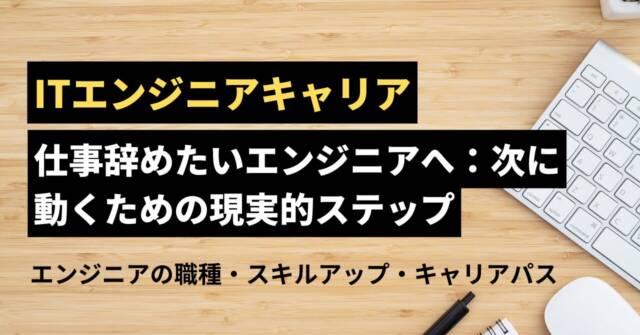
ITエンジニアとして働く中で、ふと頭をよぎることがあります。
「マジでもう、辞めたい。」
無理もありません。
急激に進化する技術、終わらない学習プレッシャー、職場の理不尽、人間関係のストレス。
気がつけば、自分が何のために働いているのか分からなくなる瞬間があります。
しかし、感情のままに会社を飛び出すのは非常に危険です。
辞めたあと、何をするのか? どう生きるのか?
ここを具体的に考えていないと、さらに深い絶望に落ちる可能性があります。
この記事では、「辞めたい」という衝動に駆られたエンジニアの方が、絶望に落ちず、次に進むためにやるべき現実的なステップを整理してご紹介します。
生き延びるために、ここから一緒に考えていきましょう。
ITエンジニアキャリア
🟡 ITエンジニアキャリア
📌 ITエンジニアとしてのキャリアパスや働き方を解説
├─ITエンジニアの仕事内容とキャリア完全ガイド
├─システムエンジニアの今後|需要と将来性は?
├─未経験者向け ITエンジニア適性診断チェック
├─フロントエンド vs バックエンド:キャリア選択の判断基準
├─アプリエンジニアからインフラエンジニアに転向すべきタイミングとは?
├─Mac版ショートカット早見表【2025年最新版】
├─エンジニアの作業効率UP!WindowsとMacのショートカット完全比較
├─Windows版ショートカット早見表【2025年最新版】
├─スクラム開発の設計とは?スプリントごとの進め方と成功のコツ
└─仕事辞めたいエンジニアへ:次に動くための現実的ステップ
🔵 ITエンジニア職種ガイド
📌 ITエンジニアの職種ごとの仕事内容や必要スキルを解説
🟢 ITエンジニア転職戦略
📌 エンジニア転職を成功させるための戦略や準備を解説
🟣 フリーランス・副業戦略
📌 フリーランスエンジニア・副業の始め方や働き方を解説
なぜITエンジニアは「辞めたい」と思うのか?

ITエンジニアとして働く中で、多くの人が心を削られる理由はいくつかあります。ここでは、その背景を整理していきます。
- 終わりなき技術習得へのプレッシャー
次々と生まれる新技術に追いかけられ、学び続けなければならない重圧が常にのしかかります。 - キャリアの不透明さと将来不安
努力の結果がどう実るのか見えず、将来に対する不安が募っていきます。 - 劣悪な労働環境と人間関係ストレス
理不尽な評価制度や、現場ごとの人間関係のストレスが、積み重なって心を蝕みます。 - 構造的な不平等・不公平への嫌悪
リスクを現場に押し付け、成功は上層部の手柄にするような文化が、現場の人間に深い絶望感を植え付けます。 本来、管理者やリーダーが人の上に立てるのは、相手に教え、導く知識と経験を持っているからに他なりません。 部下に教えることによって信頼を得て、その感謝の気持ちで指示に従ってもらう—— それが組織の本来あるべき姿です。 しかし、教えもせず、責任も取らず、ただ命令だけをする管理者が溢れた結果、 組織全体の信頼が崩壊し、現場の士気は音を立てて崩れていきます。
仕事を辞めた後に「詰まない」ために絶対すべき準備
会社を辞めたいと強く思っても、勢いだけで行動すれば、あっという間に生活が立ち行かなくなってしまいます。現実を直視し、最低限押さえるべきポイントを確実に準備しておくことが、生存確率を左右します。
生活費の最低ラインを具体的に計算する
まず最初に、毎月かかる固定費と生活費を現実的な数字で洗い出しましょう。例えば、都心部で一人暮らしをしている場合、家賃8万円、水道光熱費1万円、通信費1万円、食費3万円、雑費1万円で、生活コストは月14万円程度になります。
ここに加えて、会社を辞めた場合には国民年金:約16,000円/月、国民健康保険:地域によるが目安約15,000円/月が新たに発生します。
これらを含めると、生活費はおおよそ月17万円〜18万円となります。
さらに、急な医療費や突発出費に備えて、安全率として1.3倍を掛けておくと現実的です。
計算式にすると、 18万円 × 1.3 = 23.4万円/月。
| 項目 | 金額(円/月) |
|---|---|
| 家賃 | 80,000 |
| 水道光熱費 | 10,000 |
| 通信費(スマホ・ネット) | 10,000 |
| 食費 | 30,000 |
| 雑費 | 10,000 |
| 国民年金 | 16,000 |
| 国民健康保険 | 15,000 |
| 合計(基本生活費) | 170,000~180,000 |
| 安全率1.3倍適用後 | 222,300~234,000 |
これに半年分を掛けると、 23.4万円 × 6ヶ月 = 約140万円が最低限必要な生活防衛資金になります。
余裕を持って12ヶ月想定なら、約280万円が安全圏となります。
ここまで試算して初めて、「会社を辞める」「独立する」という選択肢が現実味を帯びてきます。表面上の支出だけを見ず、強制支出やリスクも含めた本当の生活設計をしておきましょう。
現時点のスキル棚卸しと市場価値確認
スキル棚卸しというと、「C言語できます」「Linux触ったことあります」といった資格リスト的な自己申告になりがちですが、それでは現場では通用しません。本当に問われるのは、「トラブルが発生したときに自力で対応できるか」という一点に集約されます。
たとえば、C言語を学習したことがあっても、ポインターを正確に扱えないなら、実務では使い物になりません。Linuxも、インストール経験があるだけでは不十分で、トラブル発生時にログを解析し、原因を特定して解決できるかが問われます。
このため、自分のスキル棚卸しをする際には、以下の観点でチェックしましょう。
- 単に「知っている」「触ったことがある」レベルではなく、「問題解決できるレベル」に到達しているか?
- 資格や学歴ではなく、現場で起きるトラブルに対して自力で対処できる実績があるか?
- もし現場投入された場合、自分は「自走できる」か、それとも「常に誰かの指示待ち」か?
市場価値を確認する場合も、求人情報や案件情報をリサーチしながら、要求されている実務経験(●年、●案件、トラブル対応経験必須など)と自分の経験を比較しましょう。資格や肩書きではなく、実績と実務対応力だけが評価されるのが、IT業界のリアルです。
半年間「無収入」でも生き延びるプラン作成
独立後は、収入がすぐに発生するわけではありません。むしろ、最初の半年間から1年以上、無収入に近い状況が続く可能性を前提にプランを立てる必要があります。
何を選ぶかによって、収益化までの期間はある程度想像がつきます。現実的な目安は以下の通りです。
| 独立後の選択肢 | 収益化までの目安期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| ブログ運営 | 1年〜3年 | 検索流入が伸びるまで時間がかかる。途中で心が折れるリスク高。 |
| YouTube運営 | 1年〜2年 | 今の旬を逃すと3年超えることもある。機材・編集コストも無視できない。 |
| 個人開発(アプリ・ツール) | 半年〜1年 | 初期に稼ぐにはクラウドソーシング併用必須。ただし手数料が高い。 |
| クラウドソーシング作業 | 即時〜3ヶ月 | すぐ収入にはなるが、単価が非常に低い。消耗戦覚悟。 |
※注意:上記の目安は、専業(フルコミット)で取り組んだ場合の期間です。会社勤めをしながら並行で進める場合、2倍以上の時間がかかる可能性も十分にあります。リソースの分散を前提に、さらに長期戦を覚悟してプランを立てましょう。
このように、選択肢によって収益までの期間は大きく異なります。安易に「半年分あれば大丈夫」と考えるのではなく、自分が選ぶ道の収益化タイムラインを見据え、必要資金を設計しましょう。
ITエンジニアが次に進むための3つの選択肢
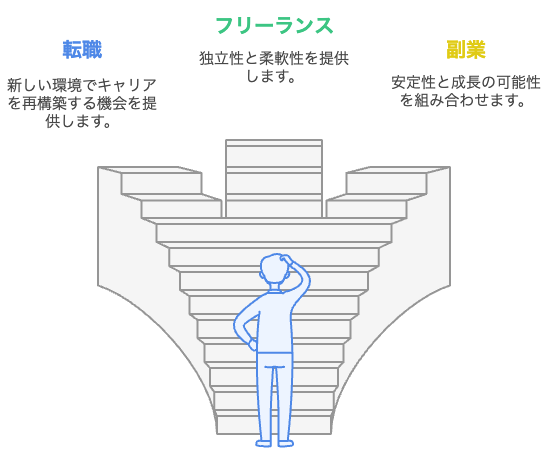
一般的には、「辞めたい」という衝動に駆られたとき、感情に任せず冷静に進路を見極めるべきだと言われます。しかし、実際の現場感覚では、会社と本気でぶつかって飛び出すような人間ほど、その後の人生をうまく切り開いている例も少なくありません。
特に印象的だったのは、新卒で入社し、2〜3年で自分のスタイルを確立し始めた若手たちの動きです。私はメンターとして彼らを育ててきましたが、優秀な人間ほど早々に次のステージへ飛び出していきました。中でも、中国人エンジニアたちは次の職が決まっていなくても名刺を配りまくり、自己アピールを怠りませんでした。
彼らを見て痛感したのは、グローバルで見れば、生き残るのは「迷ったら動く」側の人間だということです。日本人は慎重すぎる傾向があり、出遅れれば簡単に置き去りにされる時代に入っています。
重要なのは、感情のエネルギーを無謀に爆発させることではなく、爆発したあとに「自分で選び、自分で責任を取る覚悟」を持てるかどうかです。 今持っているスキルをどの道に活かすかによって、未来は大きく変わります。ここでは、現実的に取り得る3つの選択肢を紹介します。
選択肢①:別のIT企業に転職してキャリア再構築
今いる職場に限界を感じた場合、別のIT企業へ転職することで年収や待遇を改善する道は確かに存在します。しかし、私自身の経験から言えば、転職しても業種を変えない限り、職場環境や文化はほとんど変わりません。
待遇(年収)が上がることは確かでも、やる仕事の本質は変わらず、職場の閉塞感や理不尽さもそのままスライドされることがほとんどです。もし転職を選ぶなら、「環境を変えたい」という期待は捨て、「給料が上がるから割り切って働く」という割り切りができるかどうかが重要です。
私自身も、年収アップを受け入れ、定時中は完全に仕事と割り切って耐える道を選びました。しかし、結局は耐えきれず、最終的には独立することになりました。
転職で成功するかどうかは、「仕事を割り切れるかどうか」でほぼ決まります。本気で環境を変えたいなら、業種そのものを変えるか、いずれは独立を見据える必要があるでしょう。
選択肢②:フリーランスエンジニアとして独立準備
会社に属さず、フリーランスとして独立する道も現実的な選択肢のひとつです。自分で案件を選び、働き方をコントロールできるメリットは大きいですが、その反面、収入が不安定になるリスクも抱えることになります。
ここで気をつけたいのは、「ただ自由に働く」という甘い幻想に飲まれないことです。私自身、独立初期にこのイメージで動いて失敗した経験があります。
私がこの歳になるまで飢え死にせずに生き延びてこれた理由は、明確なローテーションを組んだからです。それは、現場に契約社員として出て資金を確保し、一定額が貯まったら即座に自分のビジネスに挑戦するというサイクルです。
その過程では、必ず未知の領域に直面します。私の場合、企業向けシステムには精通していたものの、CtoCサービス、ネット集客、SNS活用といった領域は全くの未知であり、何度も挫折を味わいました。
そんなとき出会ったのが「キャリアブレイク」という考え方です。エンジニアとしての軸は保ちつつも、自分にない新たなスキル領域を学び直す期間を意図的に取る。それによって、再び生き延びるための道筋を作ってきました。
資金確保 → フリーランス業務 → キャリアブレイク。このローテーションを回し続けた結果、今は「資産ブログ」という形で、徐々に自分自身のビジネス基盤を築きつつあります。
ただ自由を求めるだけでは、必ず行き詰まります。戦略的な資金管理とスキル拡張を前提にしたローテーション設計が、生き延びるためには絶対に必要です。
選択肢③:副業・独学をしながら次のステージを作る
会社に勤めながら副業や独学を進め、徐々に独立を目指すという戦略は、一見堅実に見えます。しかし、現実はそんなに甘くありません。
私自身もかつて同じ道を模索しましたが、実際には無理でした。会社員でいる以上、どんな事情があろうと、プロジェクトや売上目標といったノルマを達成することが最低条件になります。どれだけ独立準備を意識しても、現実には「ノルマ最優先>独立準備」という構図に縛られ、時間も気力も奪われていきます。
さらに、好調な時期には「このままでもいいかもしれない」と思ってしまい、気がつけば10年、20年が過ぎ去ってしまうのが普通です。私もそうでした。 そしてある日突然、リストラ、降格、転職難民という現実が襲ってきます。周囲には、生活が立ち行かなくなり、家族がバラバラになったり、若い上司の鞄持ちとして居場所を失いながら縋り続ける者たちがいました。
結論として、副業準備をしてから辞めるなどという発想自体が甘いということです。 辞めたければ、辞める。 それが唯一の道です。
辞めるときには、会社側から「契約不履行だ」「損害賠償だ」と脅されることもあります。しかし、最終的には「職業選択の自由」が憲法で保障されています。私自身、法務部とのやり取りも経験しましたが、すべて押し切ってきました。
人生は待ってくれません。 今この瞬間、行動できるかどうか。それが未来を分けます。
今すぐ動くべき行動リスト
悩んで止まっているより、まずは小さな一歩でも手を動かすことが、圧倒的に生存率を高めます。ここでは、すぐにでも着手できる具体的なアクションを整理しました。
登録だけでもしておくべきフリーランスエージェント3選
転職だけでなく、フリーランスとして働く道も視野に入れるなら、エージェントへの登録は早めに済ませておくべきです。登録しておくだけで、案件情報や単価相場を把握でき、いざ動きたいときに即スタートダッシュを切ることが可能になります。
-
レバテックフリーランス
:ITエンジニア特化型。高単価案件に強く、サポート体制も手厚い。
-
アビリティクラウド
フリーランス向け営業支援に特化。独立後も案件獲得をバックアップしてくれる。
-
エンジニアのプロ契約なら【Pe-BANK】

(ピーイーバンク):地方在住でも案件紹介が可能な全国対応型。長期安定案件に強み。
無料でスキルチェックできるサービス
自分のスキルが本当に市場に通用するのかを客観的に知るには、スキルチェックサービスの活用が効果的です。現状を可視化することで、今後磨くべきポイントも明確になります。
- paizaスキルチェック:プログラミング能力を客観的に数値化できる
-
テックアカデミー無料相談

:ITスキルと適性に合わせたキャリア診断が可能
-
TECH::EXPERT

:テックキャンプでは、入校の際に経歴や年齢は問われません。
副業エントリーだけでも始めておく意味
副業案件にエントリーするだけでも、行動履歴が積み上がります。たとえ今すぐ案件を受注しなくても、プロフィール作成や案件検索の経験が、いざという時に役立ちます。
まとめ:動かなければ何も変わらない、エンジニア人生を自分で選べ
未来は、行動した人間だけに開かれます。現状に不満を抱えているなら、悩み続けるよりも、小さな一歩でもいいから動き出すことが、人生を変える唯一の方法です。
転職を選ぶにせよ、フリーランスを目指すにせよ、副業を始めるにせよ——。どの道にもリスクは存在します。しかし、何も動かないことこそ、最大のリスクだという現実から目を背けてはいけません。
エンジニア人生を「選ばされる」のではなく、自分の意志で「選ぶ」。 それができるかどうかで、5年後、10年後の景色はまったく違ったものになります。
悩み続ける日々を終わらせ、今日から行動を始めましょう。



